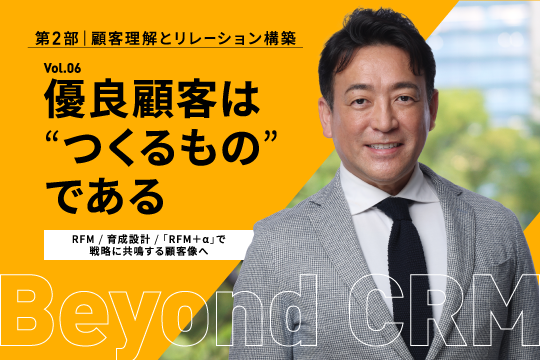
スマートウィル代表坂本によるコラムシリーズ第二弾の第6回をお届けします。
マーケティングの現場で「優良顧客」という言葉が使われるとき、それはしばしば「自然に残った高LTVの顧客」や「リピーター」のような、結果的に良かった人たちを指して使われることが多くあります。しかし、優良顧客とは本来“つくる”ものであり、企業が望む未来像や経営戦略に共鳴し、共に歩んでくれる顧客像を設計することが、CRM戦略の中核となるべきです。
RFMで“過去”を捉え、+αで“未来”を設計する
RFM(Recency・Frequency・Monetary)は、CRMの基礎として有効なフレームワークであり、購買の「直近性」「頻度」「金額」という観点から顧客セグメントを可視化するものです。これにより、リピーター予備軍やハイバリュー層を発見することができます。
しかし、RFMはあくまで「これまで」どんな付き合いをしてきたかの分析にすぎません。私たちスマートウィルでは、そこに「+α」――戦略的視点に基づく将来性の評価を加えることで、真に育てるべき優良顧客像を明らかにしています。
この「+α」とは、たとえば以下のような要素です:
- 予約や来店時の行動ログ
- メールやLINEへの反応傾向
- Webマイページやアプリの閲覧履歴
- スタッフとの接点履歴や接客評価
- ブランドに対する共感性・SNS上の発信傾向
これらの行動履歴をBoCRM上で統合的に把握することで、売上という結果指標ではなく、「関係の深まり」そのものをモニタリングし、適切なタイミングで次の一手を打つことが可能になります。
貴社の戦略に“共鳴”する人を、優良顧客と呼ぼう
大切な視点は、「優良顧客」は、他社と比較して客単価が高い人ではなく、貴社の方針や価値観に共鳴し、共に育ってくれる存在でよいということです。
たとえば:
- 高価格帯商品にこだわらないが、ブランドの思想に深く共感している顧客
- 頻度は多くないが、紹介やクチコミを積極的にしてくれるファン
- 来店頻度が伸び悩んでいるが、LINEやDMの反応は常にポジティブ
こうした顧客は、数値で見える「売上」では測れない潜在価値を秘めています。CRMの本質は、売上至上主義から脱し、「関係性」という視座で経営資源を配分することにあります。
「黒革の手帳」をデジタルで、共有で。
従来は、店頭の“敏腕スタッフ”が紙の「黒革の手帳」に記録していたような情報――会話のちょっとした気づきや好みの変化、表情のニュアンス――を、デジタルで組織的に蓄積・活用できる仕組みが求められています。
BoCRMでは、接点ログや行動データ、コミュニケーション履歴を一元管理し、誰もが「関係の進行度」を把握しながら最適な対応ができるよう支援しています。“関係を育てる”という発想が、属人的な接客力に頼らずに再現できる環境をつくること――これこそが、CRMにおける競争力の源泉です。
次回予告
接点は“配置”ではなく“設計”せよ
― 顧客行動に基づくOMO・CXデザイン ―
顧客の利便性を起点とした「接点設計」へ。配置型マーケティングから、設計型CRMへ転換する鍵とは?
【Smartwill’s 視点】
優良顧客を“発見する”のではなく、“共につくる”視点へ。
売上ではなく「関係性の動き」に注目する評価軸。
そして、数字に見えない共鳴力を、RFM+αで読み解く。
これが、スマートウィルが提唱する「顧客戦略の再設計」です。
-
日本生命保険相互会社にてリテールマーケティング戦略の構築に携わった後、日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社(現 シティグループ・キャピタルパートナーズ合同会社)に参画。企業買収(PE投資)ビジネスにおいて、マーケティング戦略担当として主にリテールビジネス領域の投資先企業の経営支援を行う。その後、テレマーケティング事業のリーディングカンパニーである株式会社ベルシステム24にて、社長室長、執行役員営業企画室長、専務執行役・COO(最高執行責任者)などを歴任し、事業運営および成長戦略を牽引。あわせて日本テレマーケティング協会常任理事も務めた。
2010年に合同会社スマートウィル(現 株式会社スマートウィル)を設立。CRM(顧客関係管理)を軸としたマーケティング戦略・組織変革支援を行う。
2012年より青山学院大学大学院 国際マネジメント研究科(MBA)にて講師を兼任し、「CRM戦略」を担当。
2014年には『この1冊ですべてわかる「CRMの基本」』(日本実業出版社)を刊行し、累計発行部数19,200部(第9刷)を超える。
2025年、東京都議会議員に初当選(世田谷区選出)。現在は、民間企業で培ったマーケティングおよび経営の知見を生かし、都政にも取り組んでいる。







